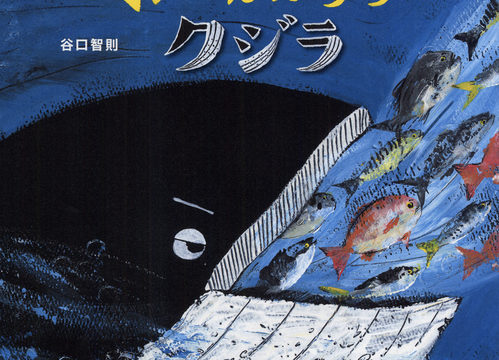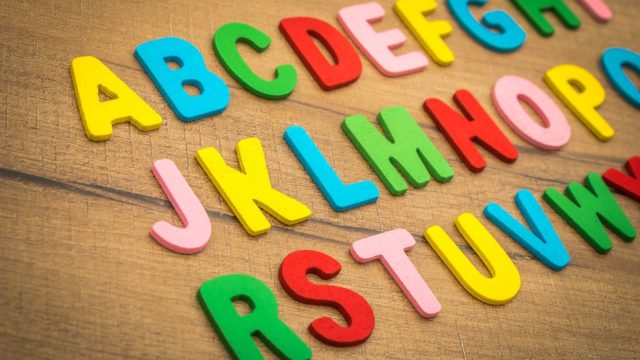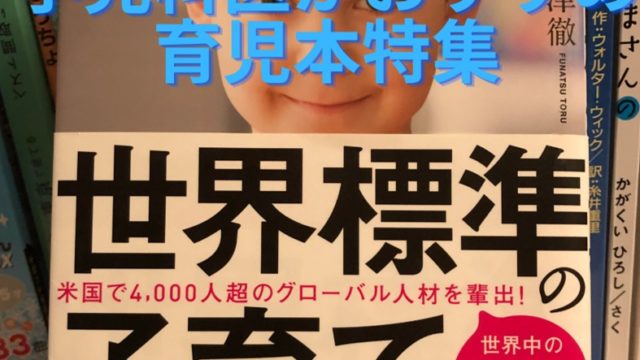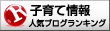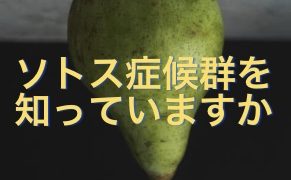小児科でよく出される薬の種類とその特徴をわかりやすく解説します

小児科に行くといつも出される薬はありませんか?
子どもに飲ませているけど本当に必要なのか?一体何のために飲むのかきちんと理解している親御さんは少ないと思います。
そこで今回は小児科でよく出される薬についてジャンルごとに特徴などをわかりやすく解説していきます。
去痰剤
- カルボシステイン
- ムコソルバン
去痰剤は子どもの風邪でよく出されますが、名前の通り、痰を出しやすくする作用があります。
子どもは大人に比べて自分で痰や鼻水などを出すのが苦手なことが多いです。
去痰剤を飲むことによって痰の排出を促すことができます。
赤ちゃんでも内服可能な小児科でももっとも処方されることの多い薬です。
鎮咳薬
- アスベリン
- アストミン
- メジコン
- プロチン
咳止めを使用する目的は咳による体力の消耗や睡眠障害を取り除くことです。
経験的には劇的な効果はありませんのであくまでも補助的に使うイメージです。
解熱剤
- カロナール
- コカール
- アンヒバ
- アセトアミノフェン
解熱剤も小児科ではよく使われますが、あくまでも頓用での使用が原則です。
解熱剤を使うことで発熱による体力の消耗を抑えたり、体の不快感を取り除きます。
3か月未満の乳児では重症細菌感染症のリスクもあり、症状を隠してしまう可能性があるので使わないでください。
制吐剤
- プリンペラン
- ナウゼリン
嘔気があるときに使用します。
副作用で錐体外路症状(振戦など)が出ることがあります。このような症状がみられたらすぐに病院を受診してください。
抗ヒスタミン薬
アレルギー反応によって放出されたヒスタミンが受容体に結合するのを阻止してヒスタミンによる様々な症状(かゆみ、じんましん、鼻閉など)を抑制します。
抗ヒスタミンは世代ごとに分けられています。
- ポララミン
- ぺリアクチン
- ザジテン
- アレグラ
- アレジオン
- ザイザル
- セルテクト
- ゼスラン
第1世代と違い脳に移行しにくいので眠気やけいれんを誘発するといった副作用も少ないです。
できれば第1世代よりこちらを使用するほうが良いでしょう。
ロイコトリエン受容体拮抗薬
- プランルカスト
- モンテルカスト
アレルギーに関与するロイコトリエンの受容体を阻害します。
主に喘息のコントローラーとして使用します。
抗菌薬について
基本、子どもの感染症はウイルス感染が原因です。
そのため原則抗菌薬は不要なことがほとんどですが、溶連菌が検査で陽性だったり肺炎が長引いたりする場合は細菌感染の関与が疑われますので抗菌薬を投与することがあります。
ですが抗菌薬をむやみに使ってしまうと、耐性菌を増やしてしまいますし、後から原因菌が検出されなくなり、症状が良くならなかった場合に診断に困ってしまいます。
ですので抗菌薬を使う際は本当に必要かどうか十分に検討する必要があります。
まとめ


今回は小児科でよく出される薬についてまとめてみました。
子どもに薬を与える前にしっかりと適応があるのか確認できるといいですね。